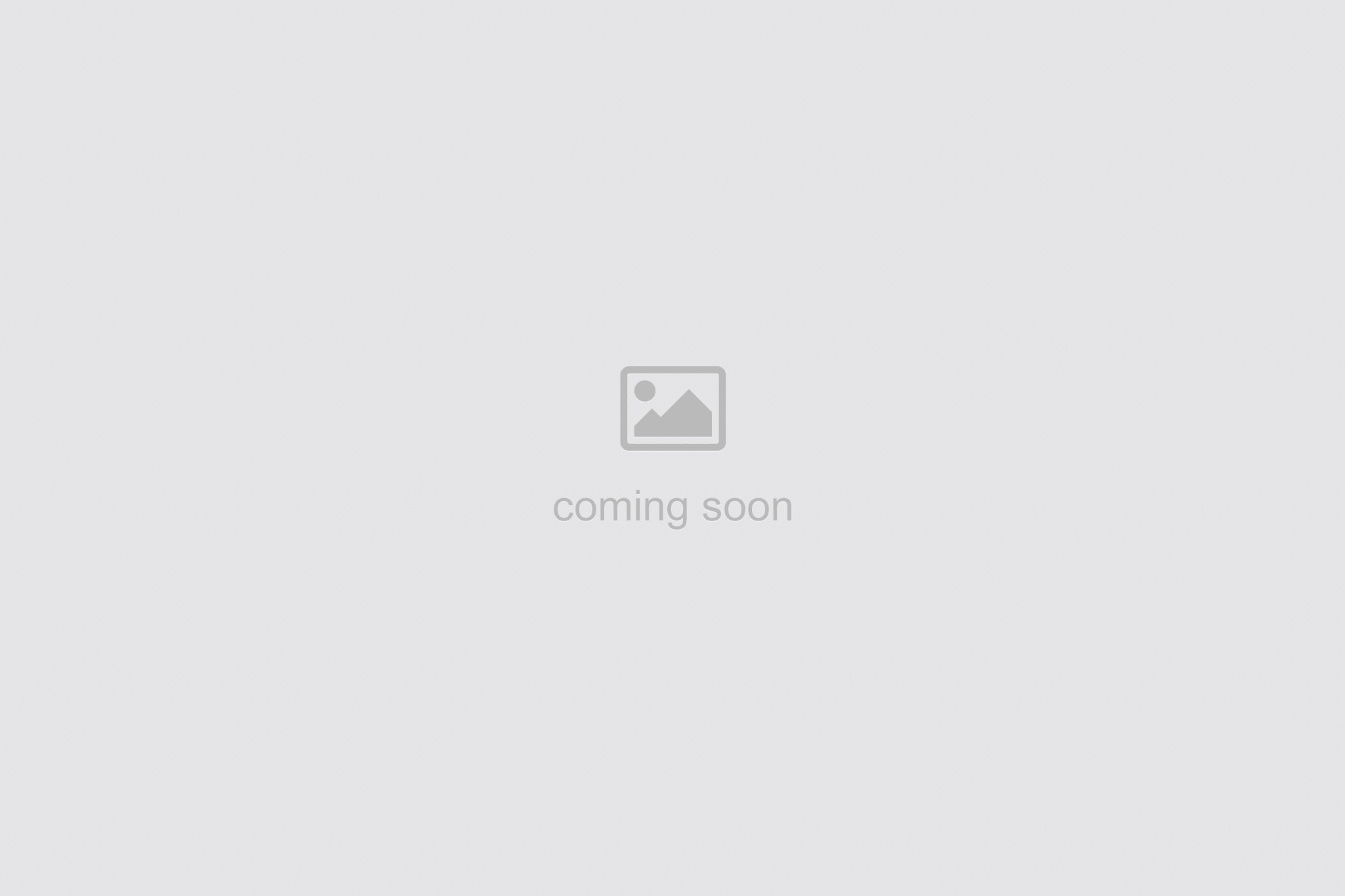最新の記事
くまりはN!S!T!「抗コリン作用と栄養障害」
カテゴリ:医療機関の方へ,くまりはNST!
注目オススメ
くまりはN!S!T!「抗コリン作用と栄養障害」 松本彩加(サルコペニア・低栄養研究センター)
薬と栄養には深い関係があります。今回はその中でも、薬の「抗コリン作用」についてお伝えします。
抗コリン作用とは、体内でアセチルコリンという神経伝達物質の働きを抑え、副交感神経の働き(図1)を抑制する作用のことを指します。このアセチルコリンは、全身のさまざまな臓器に影響を与えるため、抗コリン作用を持つ薬は多くの身体機能に影響を与える可能性があります。
抗コリン作用を治療の目的として用いる例として、過活動膀胱や胃痛、腹痛の治療薬があります。しかし、この作用が副作用として現れる場合もあり、特に以下のような症状は栄養状態に悪影響を与える可能性があります。
● 唾液の分泌が減り、口が乾燥することで食べ物を飲み込みにくくなる
● 消化管の動きが低下して食欲が減少する、また便秘になりやすくなる
● 眠気や認知機能の低下により、食事に集中できなくなる
抗コリン作用は総合感冒薬や抗アレルギー薬の一部、抗うつ薬、抗精神病薬など、さまざまな薬に含まれています。特に高齢者は、複数の病気を抱え、同時に複数の薬を処方されているポリファーマシーであることが多く、抗コリン作用による副作用が出やすくなります。そのため、抗コリン作用の強さを数値化し、リスクを評価するための「抗コリンリスクスケール」というツールが開発されています。日本でも今年、日本老年薬学会が日本版抗コリンリスクスケールを発表し、高齢者に対する抗コリン作用の影響を評価することが推奨されています(図2)。
抗コリン作用のある薬を服用している場合は、食事の様子や体重の変化に注意し、必要に応じて薬の調整や栄養サポートを受けることで、栄養状態の維持や改善が期待できます。
抗コリン作用とは、体内でアセチルコリンという神経伝達物質の働きを抑え、副交感神経の働き(図1)を抑制する作用のことを指します。このアセチルコリンは、全身のさまざまな臓器に影響を与えるため、抗コリン作用を持つ薬は多くの身体機能に影響を与える可能性があります。
抗コリン作用を治療の目的として用いる例として、過活動膀胱や胃痛、腹痛の治療薬があります。しかし、この作用が副作用として現れる場合もあり、特に以下のような症状は栄養状態に悪影響を与える可能性があります。
● 唾液の分泌が減り、口が乾燥することで食べ物を飲み込みにくくなる
● 消化管の動きが低下して食欲が減少する、また便秘になりやすくなる
● 眠気や認知機能の低下により、食事に集中できなくなる
抗コリン作用は総合感冒薬や抗アレルギー薬の一部、抗うつ薬、抗精神病薬など、さまざまな薬に含まれています。特に高齢者は、複数の病気を抱え、同時に複数の薬を処方されているポリファーマシーであることが多く、抗コリン作用による副作用が出やすくなります。そのため、抗コリン作用の強さを数値化し、リスクを評価するための「抗コリンリスクスケール」というツールが開発されています。日本でも今年、日本老年薬学会が日本版抗コリンリスクスケールを発表し、高齢者に対する抗コリン作用の影響を評価することが推奨されています(図2)。
抗コリン作用のある薬を服用している場合は、食事の様子や体重の変化に注意し、必要に応じて薬の調整や栄養サポートを受けることで、栄養状態の維持や改善が期待できます。
広報誌誌面はこちらから