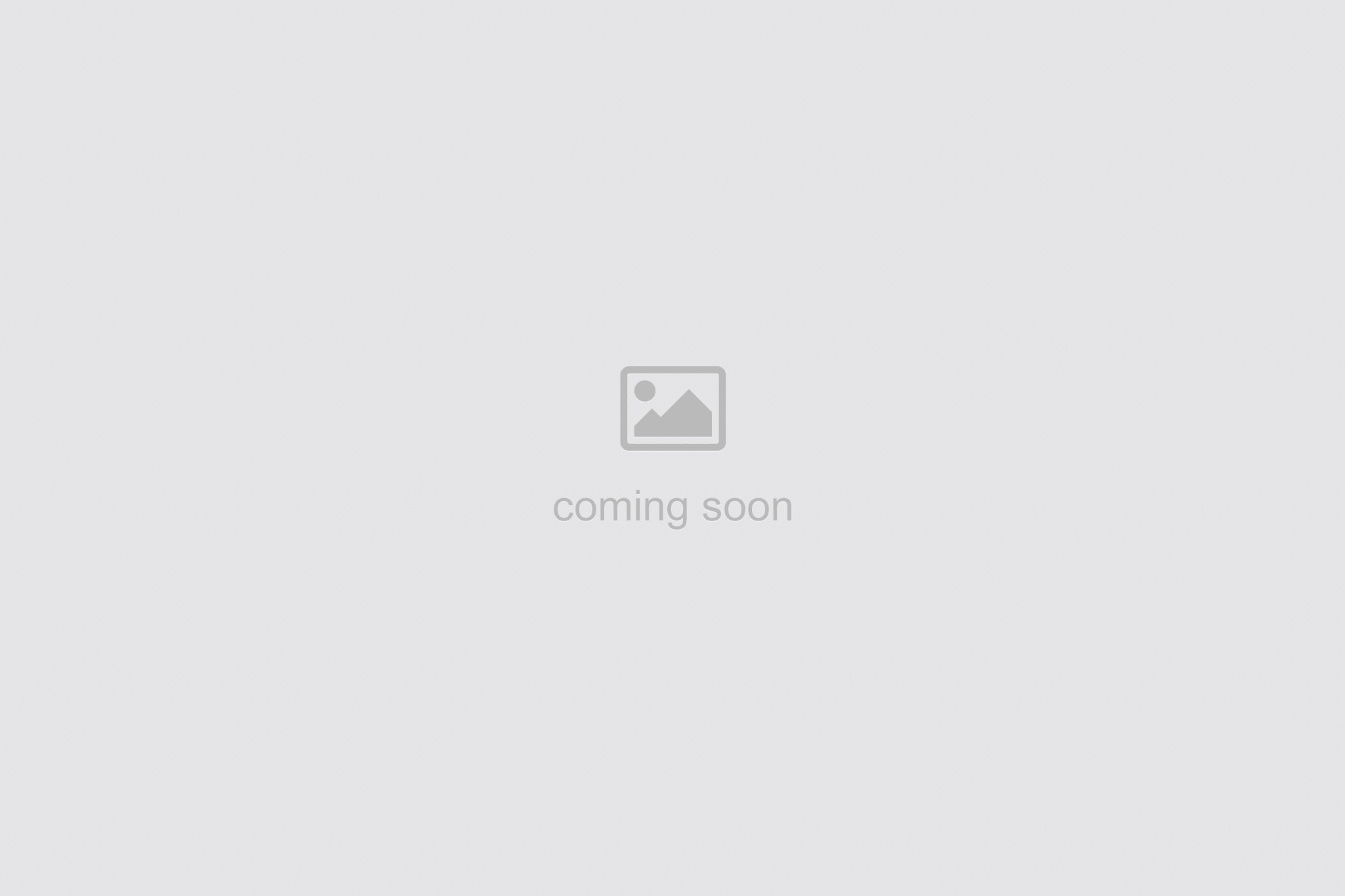最新の記事
災害研修・訓練
注目オススメ
事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)とは?
事業継続計画(以下BCP)とは災害時に事業を中断しないこと、または中断した場合にいかに復旧・再開するかの経営戦略計画のことです。
医療機関においては事業は診療を意味し、災害時に病院の機能をできるだけ維持・復旧し診療を継続(また災害によって発生する傷病者の対応)するための方針や行動計画をまとめたものです。
あらゆる災害を想定し、診療機能・建物の存続が危ぶまれる際の対応(患者移送、病院避難等)も盛り込む必要があります。
熊本リハビリテーション病院では平成28(2016)年の熊本地震の後BCPを策定しておりましたが、なかなか内容に沿った訓練や研修ができておりませんでした。
今年度災害対策委員会の下部組織として企画・作業部会を発足し、発災時の初動対応を中心に研修・訓練を実施しています。
災害発生時のCSCA
災害発災直後は当然の事ながらあらゆる混乱が生じています。
建物の被害状況、ライフライン、スタッフの稼働、近隣の被災状況、災害によって生じる負傷者……。
病院自体が被災している状況で通常を遥かに超える負傷者対応(=医療ニーズ)が発生し、助かる命が救えないということはこれまでの大きな震災で起こったことです。
災害はいつどのように起きるかわかりませんが起きてから考えていては到底太刀打ちできません。
混乱の中、いかに病院の機能を継続し対応を行うか、これについては以下のCSCATTTが重要かつ基本だと言われています。
C[Command&Control]指揮・連携
S[Safety]安全
C[Communication]情報伝達
A[Assessment]評価
T[Triage]トリアージ
T[Treatment]治療
T[Transport]搬送
TTTは実際の医療活動であり、これらを行うためにはCSCAの確立が最重要であり最優先事項であるとされています。
混乱した中で安全を確保し指揮命令系統を確立することで適切な情報伝達や指示を行い、関係機関との調整連携を図り病院の方針を決定する、という流れになっています。
あらゆる災害(地震、台風、洪水、サイバーテロなど)においてこのCSCAの確立を行う必要があります。
今年度はこのCSCAの考え方にもとづき、発災時の初動対応を学び、研修を行っています。
クロノロジー演習(災害対策本部記録演習)
8月から9月にかけては上述した災害発災時の初動対応やCSCAについての動画研修およびEMIS(広域災害・救急医療情報システム)入力演習を行いました。
(EMISについてはこちら→厚生労働省のページへ *現在新システムの導入が進められています)
10月に入り本格的な研修・訓練としてまずはクロノロジー訓練を(災害対策本部記録演習)行いました。
災害時にはあらゆる情報が飛び交い、状況も刻一刻と変化していきます。
院内で発生している状況を適切に把握し適格な判断をするには時系列で情報を整理しないといけません。
この手法をクロノロジーと言います。
フォーマットは決まっており、連絡を受けた(または指示や連絡をした)時間、誰から誰へ、内容を項目として時系列で記載していきます。
訓練では寸劇を行い本部長役と連絡係役のやりとりを聞いて内容を記載していきました。
一度台本の内容を一通り読み上げ、更に本番ではゆっくりと進めましたがそれでも書き取るのに四苦八苦しているようでした。
また、聞いた内容を書き留めるだけではなく適宜情報を整理し、それを元に本部長指示の元検討を行った内容を方針としてまとめる作業が必要です。
当日は熊本大学病院災害医療教育研究センター 特任助教 内藤久貴先生ならびに災害医療教育研究コーディネーター 馬渡博志氏にカリキュラム作成から講義、訓練の指導まで行っていただきました。
一同情報の集約、記録の重要性を痛感いたしました。
災害時の資源管理について(グループワーク)
次に、災害が起こった時の資源管理についてグループワークを行いました。
今回も熊本大学病院災害医療教育研究センター 災害医療教育研究コーディネーター 馬渡博志氏に講師をお願いしました。
災害時に必要な資源と聞いて何が浮かびますか?
水・食料・電気・ガス・・・といったライフラインに関するものは当然どの業種や家庭、避難所でも必要ですね。
医療機関であれば更に
ヒト(スタッフ、関係機関等)、モノ(医療資機材、感染対策物品、等)、移動手段(患者搬送、物資輸送)、場所(活動場所、生活場所)、情報(被災状況、患者情報、近隣の状況等)
を扱い、整備していく必要があります。
グループワークでは勤務中(昼)に地震が発生した想定で、災害対策本部が発災時に必要な物とそれらをどのようにして調達するかについて意見を出し合いました。
必要な情報が本部に集約され、院内の情報を適切に発信(EMIS)することで支援を得ることができます。
また平時より災害時に必要な物が何か、どこにあるか、どう調達するかについて整理し、周知しておくことで混乱の中少しでもスムーズな対応ができます。
本部立上げ・運営訓練
そして前回までの訓練内容を踏まえ、災害対策本部立上げ・運営訓練を行いました。
今回も、もはやおなじみ熊本大学病院災害医療教育研究センター 災害医療教育研究コーディネーター 馬渡博志氏にアドバイザーとしてご参加いただきました(本当にありがとうございます)。
平日の14:30に巨大地震が発生という想定の下、本部を設置し各部署の被災状況の設定(状況付与)に基づき担当者は現場確認と本部へ報告、指示を仰ぎ方針決定するという一連の流れを実戦的に行いました。
地震発生から各状況は動画を作成し映像の指示に従って動きました。
状況付与は11、内容も極力シンプルにしましたがそれでも実際にやってみると本部はかなり騒然とし、あらゆる問題が発生しました。
お互い状況を見て軌道修正しながらなんとか課題に対して指示を出し、病院としての方針決定まで行い参加者全員にて振り返りを行いました。
振り返りでは、連絡体制の不備、マニュアルやアクションカードの見直し、記録方法やまとめ方の工夫、施設設備管理に関する教育の必要性(施設管理のスタッフではマンパワーが不足する)、などが挙げられました。
馬渡様からは「1時間だけの訓練だったのに反省点がたくさんでたことに感心しました。記録係の方は入ってきた情報を記録していただいているが、プライオリティリスト・傷病者のリストなどをつくってインフォメーションをインテリジェンスに変えていく必要がある。」
といったご助言をいただきました。
これまで実戦的な研修・訓練はあまりできていませんでしたが、訓練実施が目的ではなく、課題をみつける事が目的であると痛感しました。
今回の訓練を通し見えた課題をBCPに反映し、また研修・訓練を繰り返して災害対応力を向上したいと考えております。
最後に、今回に訓練に際して熊本大学病院災害医療教育研究センター センター長 笠岡俊志先生、特任助教 内藤久貴先生、災害医療教育研究コーディネーター 馬渡博志様に多大なるご支援とご協力を賜りました。この場を借りてお礼申し上げます。